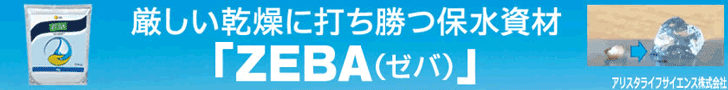搾乳の機械化と規模拡大の進展【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第233回2023年3月30日

乳搾りを機械がやる、それを初めて聞いたときには驚いたものだった。
搾るときのあの微妙な人間の指の動き、それを機械がやれるだろうか、牛が嫌がらないだろうか、傷ついたり乳房炎になったりしないだろうか。
そんな疑問をもったのだが、まったくの杞憂だった。大学の農場で初めてその搾乳機、通称ミルカーを見たのだが、牛はおとなしく搾らせていた。
ゴム製のチューブが内側についたステンレス製の細い管(カップ)を四本、乳頭につけ、そのカップの内部を電気の力で真空にし、また乳頭を圧迫して乳を吸い出す、その乳をカップの先についたホースで乳の貯留器具に送るのだというのだが、よくもまあ考えたものである。衛生面でも大丈夫とのことだ。しかも1頭当たり5分で絞れるという。
これなら飼育頭数を増やすことができる。低乳価を補うための多頭化を迫られていた酪農家は政府の勧めに応じてこのミルカー導入を考えざるを得なくなってきた。
一方、乳業会社は、牛乳の細菌数など乳質を厳しく言うようになり、牛乳の貯蔵タンクと冷却機を組み合わせたバルククーラーの導入を半ば強要した。
そこで酪農家はミルカーとバルククーラー、それをつないで乳を自動的に送るパイプラインを導入することにした。
畜舎にあるミルカーと貯蔵施設にあるバルククーラーをパイプでつなぎ、やはり電力でパイプを真空にして搾った牛乳をバルククーラーに送り、そこで急速に冷却して乳質の劣化を防ぎ、貯蔵して、それを乳業メーカーの集乳車に引き渡すようにせざるを得なくなったのである(それに対応できない農家は酪農をやめるしかなかったのだが)。
それでこのパイプラインミルカーが1970年前後から急速に普及し、搾乳にかかわる作業は道具、器械の段階を経ることなく手作業から一気に機械段階へと進むことになった。
それと同時に牧草等飼料作物の栽培にかかわる機械化も進展した。
そしてそれらは大幅な省力化と、一戸当たり飼育頭数の多頭化を可能にした。実際に多党化が急速に進んだ(注1)。
農業の機械化自体は大きな進歩だった。
しかしそれは農業の資源環境保全的性格が弱まり、農業が地球温暖化を始めとする環境問題の加害者の一員となったことを意味するものでもあった。
さらにそれは、意外な弱点をもっていた。電気などの動力源がなければ農業ができなくさせられたのである。光源、熱源としての電気ばかりでなく、動力源としての電気も不可欠となってきたのである。酪農における搾乳などはその典型であり、その問題点が明らかになるのは大震災のときだった。それを次に見て見よう。
岩手県北上山地北部のK町で酪農をいとなむNさんご夫婦のお宅でも1971(昭46)年にミルカーを導入した。20歳代だったお二人は旧来の自給的畑作経営から脱却し、山間地に適した酪農経営を発展させようとしてきたのだが、時代の変化に対応して多頭化すべく導入したのである。
そしてこのミルカー導入を契機にこれまでの3頭(うち搾乳2頭)飼育から5頭(うち搾乳3頭)に拡大(注2)した。
さらに、78(昭53)年には近隣の意欲ある酪農家5戸と共同で大型トラクターなどの飼料作物にかかわる機械を導入し、作業も共同で行うことにした。こうして飼料作にかかわる経費節減と省力化も図り、やがて80年ころには約60頭(うち搾乳約30頭)を飼育するにいたった。
しかし、労働力は二人だけ、やはり限界、60歳を過ぎるころから徐々に頭数を減らしてきたが、それでもあの日、2011年3月11日には、経産牛37頭(うち搾乳牛28頭)、育成牛10頭、合計47頭を飼育していた。これだけの頭数だと仕事が大変なのだが、3月はいまだ寒いK町、畑や草地など外での仕事もないので、朝の搾乳を終えた後夕方の搾乳までの時間、二人はゆっくり家の中で休んでいた。
そこに、あの地震が襲ってきた(この続きは次回とさせていただく)。
(注)
1.当時は農業構造政策が展開されたころ、農政は当初5頭飼えば家族労働力で他産業並みの所得が得られる自立経営になれると規模拡大を指導したものだった。そのことについては前に下記の本コラムで述べたので、必要があれば参照されたい。
本稿2021年8月19日掲載 第159回「選択的『(赤字)拡大」。
https://www.jacom.or.jp/column/2021/08/210819-53321.php
本稿2021年8月26日掲載 第160回「ゴールなき規模拡大」参照。
https://www.jacom.or.jp/column/2021/08/210826-53499.php
2.本稿2023年1月19日掲載 第223回「酪農の機械化・施設化と『混同農業』の崩壊」参照。
https://www.jacom.or.jp/column/2023/01/230119-64138.php
重要な記事
最新の記事
-
 名付けて「そんなことより解散」【小松泰信・地方の眼力】2026年1月14日
名付けて「そんなことより解散」【小松泰信・地方の眼力】2026年1月14日 -
 農林水産省「総合職」「一般職」を公募開始 エン2026年1月14日
農林水産省「総合職」「一般職」を公募開始 エン2026年1月14日 -
 森林・林業の新技術開発・実装推進シンポジウムを開催 農水省2026年1月14日
森林・林業の新技術開発・実装推進シンポジウムを開催 農水省2026年1月14日 -
 青森米増量企画「あおもり米キャンペーン」開催 JA全農あおもり2026年1月14日
青森米増量企画「あおもり米キャンペーン」開催 JA全農あおもり2026年1月14日 -
 「第21回全農全国高等学校カーリング選手権大会」青森県で開催2026年1月14日
「第21回全農全国高等学校カーリング選手権大会」青森県で開催2026年1月14日 -
 JAふじ伊豆×木村飲料静岡県伊豆・東部のご当地「伊豆レモンサイダー」新発売2026年1月14日
JAふじ伊豆×木村飲料静岡県伊豆・東部のご当地「伊豆レモンサイダー」新発売2026年1月14日 -
 ハクサイ・キャベツ農家による小学生体験授業 野菜産地の牛窓地区で初開催 JA岡山と瀬戸内市2026年1月14日
ハクサイ・キャベツ農家による小学生体験授業 野菜産地の牛窓地区で初開催 JA岡山と瀬戸内市2026年1月14日 -
 日本~アジアを繋ぐ海底通信ケーブルを運営 新事業会社を設立2026年1月14日
日本~アジアを繋ぐ海底通信ケーブルを運営 新事業会社を設立2026年1月14日 -
 国際シンポジウム「大豆育種の推進:遺伝学・ゲノミクス・バイオテクノロジー・栽培」開催 農研機構2026年1月14日
国際シンポジウム「大豆育種の推進:遺伝学・ゲノミクス・バイオテクノロジー・栽培」開催 農研機構2026年1月14日 -
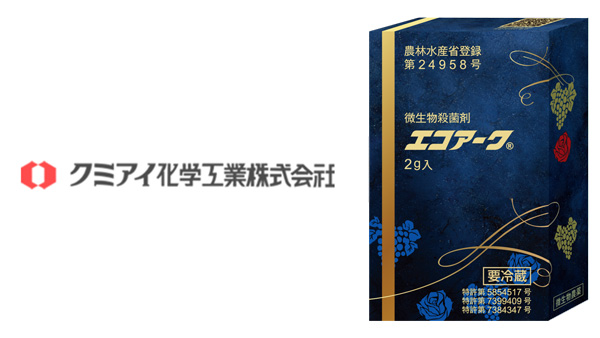 根頭がんしゅ病に高い防除効果 微生物農薬「エコアーク」販売開始 クミアイ化学工業2026年1月14日
根頭がんしゅ病に高い防除効果 微生物農薬「エコアーク」販売開始 クミアイ化学工業2026年1月14日 -
 【人事異動】(2026年2月1日付、26日付) 北興化学工業2026年1月14日
【人事異動】(2026年2月1日付、26日付) 北興化学工業2026年1月14日 -
 農と食は「最大の安全保障」 鈴木宣弘教授招きシンポ 2月10日国会内で2026年1月14日
農と食は「最大の安全保障」 鈴木宣弘教授招きシンポ 2月10日国会内で2026年1月14日 -
 「JAアクセラレーター第8期」募集開始 AgVentureLab2026年1月14日
「JAアクセラレーター第8期」募集開始 AgVentureLab2026年1月14日 -
 糸島農業高校にラジコン草刈機を贈呈 次世代の農業人材育成を支援 オーレック2026年1月14日
糸島農業高校にラジコン草刈機を贈呈 次世代の農業人材育成を支援 オーレック2026年1月14日 -
 福島県に「コメリハード&グリーン会津坂下店PRO館」25日から営業開始2026年1月14日
福島県に「コメリハード&グリーン会津坂下店PRO館」25日から営業開始2026年1月14日 -
 東日本大震災15年「原発事故被災者応援金助成活動報告会」開催 パルシステム連合会2026年1月14日
東日本大震災15年「原発事故被災者応援金助成活動報告会」開催 パルシステム連合会2026年1月14日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月14日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月14日 -
 鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月14日
鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月14日 -
 生活クラブ 新規加入で最大4000円値引き&最大5000円分クーポンをプレゼント2026年1月14日
生活クラブ 新規加入で最大4000円値引き&最大5000円分クーポンをプレゼント2026年1月14日 -
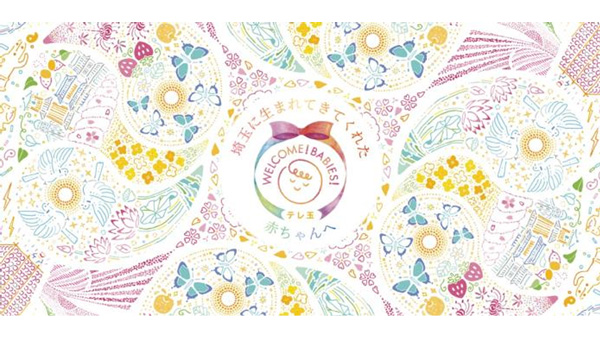 埼玉県に生まれてきた赤ちゃんへ届ける「はじめてばこ 埼玉」募集開始 コープみらい2026年1月14日
埼玉県に生まれてきた赤ちゃんへ届ける「はじめてばこ 埼玉」募集開始 コープみらい2026年1月14日