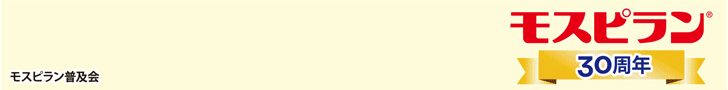平成の大合併と地方自治【小松泰信・地方の眼力】2025年10月15日
10月15日から21日まで日本新聞協会が定める新聞週間。今年の代表標語は「ネット社会 それでも頼る この一面」。

地方紙の存在意義
中国新聞(10月15日付)の社説は、「新聞業界を取り巻く環境は厳しいが、綿密な取材に裏打ちされた報道を通じ、信頼されるメディアであり続けねばならない」と気合いを入れている。もちろん他紙も同様の姿勢。
インターネット上におけるソーシャルメディア(SNS)普及がもたらす功罪を念頭に置き、「事実を確認して報道するのは長年、新聞を支えてきた背骨」とした上で、「誰もが簡単に情報を発信できる時代だからこそ、新聞は愚直に、誠実に正確な記事を読者に届け続ける必要がある」としている。
「権力監視」機能に言及し、トランプ大統領が自身に批判的なメディアに対して、名誉毀損で提訴したり、放送免許の取り消しを示唆するなど、圧力を強めていることにふれ、「身勝手な振る舞いは目に余る」と断じる。返す刀は、総務相時代に、政治的公平性を欠くと認定した放送局への電波停止の可能性に触れてと批判を浴びた、自民党新総裁高市早苗氏に向かう。
「新聞社は軍や政府の発表を垂れ流し、戦争に加担した反省が戦後の出発点にある。為政者の暴走を止める覚悟は絶対に失ってはならない」と、凜として自らに念を押す。
もちろん、「地域の誇りやアイデンティティーを育むのも大切な役割」と地方紙の存在意義も忘れてはいない。
平成の大合併がもたらす財政危機
その地方であるが、人口減少克服と東京一極集中の是正を目指し、第2次安倍晋三政権が2014年に打ち出したのが「地方創生」。国政の重要課題であるはずだが、議論や検討が深まる兆しは感じられない。
「地方創生」に先立ち、地方分権の推進に対応するため、自治体の行財政基盤を強化し、広域化することを目的に、1999年から2010年にかけて政府主導で進められたのが「平成の大合併」。これによって1999年に3,229あった市町村が、2010年には1,727にまで減少した。
日本経済新聞は、10月13日付から「迫真 平成の大合併20年」という企画を始めた。
第1回は、北海道北見市と京都府南丹市を取り上げている。
2006年3月、旧北見市が周辺の3町と合併して誕生した北見市は、「合併特例債」(05年度までに合併した市町村が対象。返済額の7割は国が地方交付税で負担し、残りの3割を合併自治体が返済)をハコモノ投資に使ったことを一因とする深刻な財政難に直面している。
そのハコモノのひとつが、合併特例債を利用して118億円かけて整備し、21年に開庁した新庁舎。
23年度の特例債の返済額は17.6億円で14年度の3倍超。人件費や物価高騰で行政経費が膨らむ中で、24年度の市庁舎の維持経費も約2億円。この結果、犠牲を強いられるのが市民。例えば、指定ごみ袋の価格は26年10月から基本的に1.5倍に引き上げ。市内の複数の保育施設は廃止となった。
京都府のほぼ中央に位置する南丹市は、2006年3月旧園部町や旧八木町の4町が合併して誕生した。
18年から市長となった元八木町職員の西村良平氏は、旧4町は財政が苦しく、合併で地方交付税の特例を当てにしたが「明確なまちづくりのプランがなかった」「優遇策につられて合併した」と本音を語っている。
減らす必要があった旧4町の公共施設の整理も思うように進まず、維持費を背負い込み、貯金にあたる財政調整基金を取り崩す事態に。このままでは基金を除き毎年16億〜19億円の収支不足が続くと見込む。
これらのように、財政危機に陥る合併自治体に対して、「住民が財政状況に気づいていないことも多い。説明を尽くして施設の統廃合などを急ぐ必要がある」と、警鐘を鳴らしているのは、宮下量久氏(東洋大学教授)。
合併自治体からの離脱を求める
合併自治体の多くが、中心市街地を活性化させるための拠点整備に取り組む。しかしその一方で、周辺部が廃れたケースも少なくない。
日本経済新聞の企画第2回(14日付)は、山口県周南市(2003年2市2町が合併)の旧熊毛町住民有志が、「合併からの離脱を可能にする特例法の制定を」目指して、21年に市からの離脱を求めて「熊毛町を取り戻そう会」を立ち上げたことを伝えている。
市中心部には駅ビル整備などで巨額の資金が投じられたが、山間部にある熊毛地区への投資はほぼなく、人口は合併後に2割減。水道料金は7割も値上がりし、地域唯一の高校も26年度には廃校とのこと。
これでは、当該地区は間違いなく廃れる。それも急速に。
「メリットはほとんどない」と憤るのは、合併直前まで旧熊毛町議を務めていた沖田秀仁氏。会のメンバーも「見捨てられたと感じる地域は全国に多いはず」と語っている。
制度的には極めて高いハードルが立ちはだかっているが、合併を後悔している各地の旧町村から、関心を集めているそうだ。
闘う地方自治
「住民の声を行政当局に届けて状況の改善につなげるなどの役割がある。地元の生活環境はもちろん、経済振興や雇用の受け皿拡大など対象は幅広い。当局が打ち出す施策に対する監視機能なども重要な役割だ」と訴え、市町村議員を「なくてはならない存在」と位置付けるのは秋田魁新報(10月1日付)の社説。背景にあるのは、議員のなり手不足。秋田県美郷町の町議選では定数割れにより初めて無投票。東成瀬村では2011年の村議選以降、4回連続で無投票。危機意識が社説子にペンを執らせた。
議員報酬額の問題も指摘されているが、衰退する地域に歯止めをかけることの難しさと責任の重さが立候補をためらわせているはず。しかし、なり手がいなければ「自治体乗っ取り」を目論む連中さえ出かねない。それは絶対に阻止すべき事項。
地方の衰退に歯止めをかけるためには、間違いなく自治力、すなわち地域住民の自己決定力が問われてくる。地域が抱える課題に皆が正面から向き合い、知恵を出し合い、決定事項には責任を果たす。そんな「闘う地方自治」の先にしか地方の創生はない。
「地方の眼力」なめんなよ
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日
シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -
 農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日
農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -
 米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日
米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -
 (471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日
(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -
 スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日
スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -
 【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日
【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -
 【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日
【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -
 【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日
【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -
 【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日
【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -
 令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日
令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -
 「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日
「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -
 2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日
2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -
 【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -
 福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日
福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -
 いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日
いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -
 三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日
三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -
 【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日