JAの活動:新世紀JA研究会 課題別セミナー
農協出資法人は経営継承の切り札 担い手確保、遊休農地防止にも2019年5月30日
農業と農地を守るため、特に水田農業で、農協が直接経営に乗り出す動きが強まっている。その形態はさまざまだが、本来、組合員の経営を支援する立場にある農協が自ら生産に乗り出すということは本末転倒とも言えるが、生産者の高齢化が進み、このままでは農業と農地の維持が難しいという現実がある。新世紀JA研究会は5月の課題別セミナーでJAによる農業直接参入の問題を探った。3つの報告を紹介する。
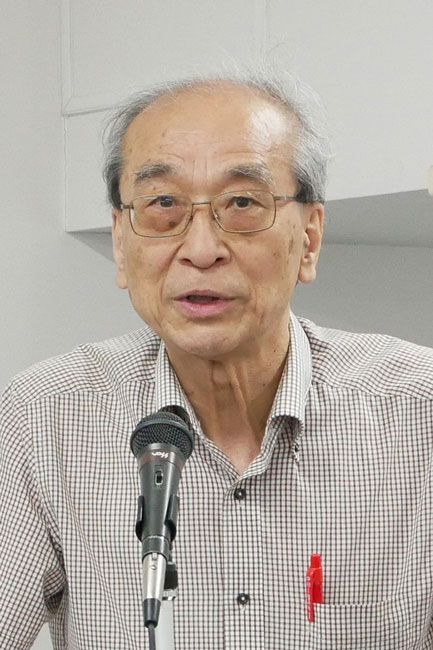 谷口信和氏
谷口信和氏
日本農業の担い手問題は新しい局面に入りつつある。それはすでに地域農業の中で担い手と認知されている大規模な農業経営が、家族経営や法人経営では後継者が、集落営農では新たな構成員が確保できず、経営継承に困難を抱える事態が各地で発生しているからである。
そこでは、小規模経営から大規模経営までが農地(農業資源)の提供者とならざるをえない事態が水田農業から畑作・果樹・施設園芸などの耕種部門全体に及ぶだけでなく、畜産・酪農など全農業部門に広がりつつある。
こうした中で、地域農業の持続的な発展を保証するためには、単に優良農地だけでなく、条件不利農地や耕作放棄地をも含めて地域農業資源を余すところなく活用することを重要なミッションとした農協による農業経営(中心は農協出資型農業法人)の存在意義が従来にも増して大きくなりつつある。
水田農業などにおいては農協出資型農業法人が1年に新規借入する面積が10haを超えるばかりか、30ha超に及ぶ場合すら発生しており、大規模な法人経営の存在が地域農業の存続にとって不可欠となっている。
◆農協直営型の経営も
一方で農協による農業経営は、1988年の第18回全国農協大会で農協が「農用地利用調整」に積極的に取り組むことを決議するとともに、1989年から農地保有合理化事業(賃貸借のみ)に着手し始めたことを契機とし、他方で1992年の新政策で農業法人化が構造政策の目標の一つとして位置づけられ、1993年の農地法改正と農業経営基盤強化促進法により、農業生産法人への法人としての農協の出資が法認されたことを起点として本格的に始められることになった(農地の権利取得を伴わない農業法人化に対して農政は積極的な関心を示してはこなかった)。
当初はもっぱら農協出資型農業生産法人として設立され、2009年の農地法改正によって農協直営型経営が新たに登場することになったが、中心はあくまで前者にある。2018年末現在でほぼ300程度の農協で合計724の農業経営が取り組まれているが、このうち農協主導型法人(農協の出資割合50%超)が229、非農協主導型法人が434(うち一般経営159、集落営農型275)、農協直営型が59となっている。
◆地域農業には不可欠
農協出資型法人では経営面積が100haを超える経営が48経営(全体の12.8%)、売上高1億円以上の主導型法人が33経営(25.0%)あり、全体としては日本の大規模経営のほぼ3%を占める存在となっている。そこでは、一方で耕作放棄地の復旧に重要な役割を発揮するとともに、他方では新規就農者研修事業等を通じて、地域農業の多様な担い手を育成する「半公共的な役割」をも担い、地域農業の維持・発展にとって不可欠の意義を有している。
こうした役割を担うことから多くの出資型法人は設立から3、4年目までは赤字経営を余儀なくされることが多いが、初期投資に基づくファームサイズと経営実績を示すビジネスサイズが照応してくる4年目以降に収支均衡から黒字に移行する傾向を有している。
◆高まる総合性の意義
今日の地域農業においては、(1)耕作放棄地、(2)新規就農者育成、(3)直売所、(4)耕畜連携を軸とした地域農業の総合化という4つの課題をめぐって家族経営の危機を主内容とする担い手問題が存在している。農協による農業経営は家族経営の補完・支援・代替機能を担いながら、これらの4つの課題に総合的に取り組むことを要請されている。
これらの課題に果敢に挑戦してきた先進的な法人の経験=歴史の波頭を整理する形で出資型法人の展開過程をまとめれば、以下の6つの局面が指摘できる。
▽第1局面=水稲作を中心とした水田農業経営から農業内のあらゆる部門への進出。
▽第2局面=農作業受託から農業経営への移行(「地域農業の最後の担い手」の位置づけ)。
▽第3局面=本来の農業経営から耕作放棄地復旧・再生、新規就農研修といった地域農業資源(土地と人)の再生・創出という新たな課題への挑戦(「地域農業の最後の守り手」の位置づけ)。
▽第4局面=小規模家族経営の経営代替・継承問題から大規模家族経営の経営代替・継承問題への対応という課題の深化(法人経営を創出する新規就農研修の登場。「地域農業の最後の攻め手」の位置づけ)。
▽第5局面=自治体から始まり、地域に存在する多様な農業関連企業(農家)へと出資者の枠を大きく広げたJA出資型法人への移行。
▽第6局面=地域農業の担い手問題への部分的な対応から総合的な対応へ(耕種部門内における多数の農業部門への進出から始まって、畜産でも複数の部門を擁する事例が出現し、直売所支援と新規就農研修事業の結合がみられる)。
こうして、今や農協による農業経営は「地域農業発展の総合的拠点」の地位を獲得するところにまで至りつつある。こうした展開を支えるには単協が総合事業展開をしていることが極めて重要であろう。
重要な記事
最新の記事
-
 【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日
【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -
 【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日
【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -
 (474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日
(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -
 和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日
和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -
 築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日
築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -
 幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日
幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -
 「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日
「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -
 大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日
大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -
 築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日
築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -
 栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日
栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -
 秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日
秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -
 農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日
農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -
 日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日
日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -
 中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日
中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -
 持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日
持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -
 札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日
札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -
 高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日
高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日 -
 高校生が森・川・海の「名人」を取材「第24回聞き書き甲子園」受賞者を決定2026年2月20日
高校生が森・川・海の「名人」を取材「第24回聞き書き甲子園」受賞者を決定2026年2月20日 -
 機能性表示食品「ことばうっかりサポート えごま油の力」新発売 J-オイルミルズ2026年2月20日
機能性表示食品「ことばうっかりサポート えごま油の力」新発売 J-オイルミルズ2026年2月20日 -
 おやつにぴったりな5種mix「亀田の柿の種 トレイルミックス」期間限定発売2026年2月20日
おやつにぴったりな5種mix「亀田の柿の種 トレイルミックス」期間限定発売2026年2月20日









































































