JAの活動:米価高騰 今こそ果たす農協の役割を考える
「令和の米騒動」と水田政策の未来 事後調整の必要とJAの機能 西川邦夫茨城大教授に聞く(1)2025年7月17日
政府備蓄米の放出で店頭の米価格が低下し始めるなか、まもなく早期米が出回る時期を迎える。生産現場には今後の米価の動向などに不安が広がるなか、2027年度からの水田農業政策の見直し議論も始まる。改めて今回の「令和の米騒動」の要因と今後の政策のあり方について茨城大学学術研究院応用生物学野の西川邦夫教授に聞いた。
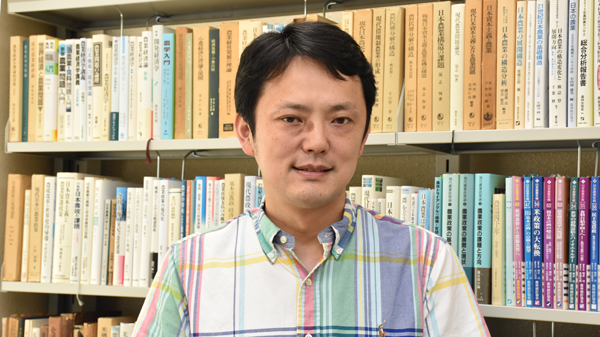 茨城大教授 西川邦夫氏
茨城大教授 西川邦夫氏
「需要見通し」に限界
――今回の米高騰の要因をどう考えますか。
需要に対して供給が足りなかったということだと考えています。
農水省の「需要見通し」に問題がありました。「需要見通し」は過去の実績に基づく推計ですから、たとえばコロナ禍では思ったより需要が減ったので需要実績が下振れし、今回は需要が思ったより増えたので需要実績が上振れしたということです。そうした急な需要の変化には「需要見通し」は対応できないようになっています。ただ、これ自体は「推計」ですからやむを得ないと思います。
しかし、そうした不安定な指標をもとに重要な政策決定を行ってきたことが一番の問題だと考えています。
23年産では需要を680万tと予測しましたが、実際は705万tでした。そして供給は661万tだったわけです。需要増の要因はインバウンド需要や、米がパンや麺より安かったこと、コロナ禍が明けて外食需要が戻ってきたことなどいろいろあります。
過剰恐れ、過剰に深堀り
供給面は減産し過ぎたことが大きい。これは、そもそもの生産量の目標設定が低めだったことと、道府県の再生協議会の中で、さらに深堀りした目標を設定したところがありました。供給過剰を非常に懸念して、一段階低めに目標を設定するということがあったため661万tという供給実績になったと思っています。
ただ、その前の年、22年からすでに流通業者からは集荷に苦戦しているという声が聞かれました。それでも減産が続いたということだと思います。
そこには、コロナ禍のときに米はかなり余って価格が下がったという記憶がありました。あのときの過剰は関係者の間では深刻だったので、減産ドライブをかけたということです。それによって22年から23年にかけて過剰が解消しました。しかし、その後も供給過剰となることを恐れて引き続き減産が続いたということだと思います。
需要と供給の少しの変化で価格が大きく変わるというのが農産物の特徴です。当時の過剰は20万t、今回の不足は40万tです。これぐらいのレベルでかなり価格が変動すると見ています。
機動性ない備蓄米放出
――備蓄米の放出、とくに小泉農相による随意契約米による米価対策についてどう評価しますか。
備蓄米の放出自体はやむを得なかったと思います。価格がこれだけ行き過ぎて高くなっていましたから。ただし、備蓄米の放出はなかなか機動的な市場対策にはならなかったと思っています。
備蓄米放出のスキームができたのは1月31日の食糧部会、その後、2月14日に江藤前農相が備蓄米放出を決定しました。そして3月に入札が実施された。この時点ですでに1か月半かかっています。そして現在までに放出が決定した81万tのうちどのくらい店頭に並んでいるかを見ると、6月8日時点ですが、実需へは一般競争入札分で3割、随意契約分で1割未満です。均すと2割程度。備蓄米放出決定から5か月経ったのに2割しか並んでいなかった。
収穫後に需給調整を
現在の米政策は、収穫前に生産調整して、そこで需給調整をしており、収穫後に需給調整する仕組みは基本的にありません。米穀周年供給・需要拡大支援事業がありますが、これは余った米に対する対策であり、足りないことに対する対策は見当たりません。
本来であれば備蓄米の放出という最終手段を使う前になんらかの対策が制度として仕組まれている必要があったと思いますが、これがなかったので、為すすべがなかった、ということになります。
昨年の8月に備蓄米を放出すべきだったという主張もありますが、今年実施された備蓄米放出の経過を考える必要があります。昨年8月に決めたとしても市場に出てくるのは12月ぐらいになるということですから、あまり変わらないと思います。
ですから収穫後に需給を調整する仕組みを設けない限りは同じようなことが起こる可能性は当然あると思います。
今は、収穫後のバッファーは「ふるい下米」しかありません。米が余っているときにはふるい下米は加工原材料等に回され、足りないときにはふるい下米から一部が主食用に上がってくる、ということですが、今回の米騒動ではふるい下米がいちばん最初になくなったわけです。ですからバッファーをどう作っていくかが課題だと思っていて、収穫後に市況に応じて主食向け、加工向けなどに振り向けていくなど柔軟に調整できる仕組みがあったほうがいいと考えます。
用途限定米穀 見直しを
ただ、現在の用途限定米穀は事前に契約ありき、営農契約書の提出の前に契約をすることを前提にしています。たとえば飼料用米や加工用米を事後的に主食用米に振り向けようとすれば、契約をし直す必要があります。それは確かに実務的に大変な問題です。そこで、契約をしなくてもいい数量を、ある程度作っておくということはあり得ると思います。
その際、もう一つ問題となるのは交付金です。飼料用米、あるいは加工用米を作るから交付金が支払われるわけですが、それを事後的に主食用米に転換すると、交付金をもらいながら主食用に仕向けることが問題となります。ですから用途別の交付金をもう少し中立的な交付金に組み替えていく必要があります。
かつて1995年に食糧法が施行されたときには農協による調整保管制度がありました。その後、作況指数が101を超えたらその豊作分を米穀機構で保管する集荷円滑化対策もできました。しかし、調整保管制度は過剰のときに大量の米が集まってきたために、農協の負担や財政負担も大変になり、うまく行きませんでした。
ただ、発想としては、これらは事後的な需給調整の仕組みだったということです。今回、備蓄米の放出はあまり機動的ではないことが分かりました。やはり事後的な需給調整を農協や流通業者などの日常業務で行えるのが望ましいと思いますから、もういちど制度づくりにトライしてみる価値はあると思います。
(にしかわ・くにお)1982年島根県松江市生まれ。2005年東大農学部地域経済・資源科学課程卒。2010年東大大学院農学生命科学研究科農業・資源経済学専攻博士後期課程修了。2014年茨城大農学部准教授、2025年茨城大学術研究院応用生物学野教授。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日
シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日 -
 農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日
農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日 -
 【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日
【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -
 スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日
スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日 -
 5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日
5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日 -
 (472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日
(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -
 山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日
山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -
 大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日
大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -
 栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日
栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -
 大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日
大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -
 愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日
愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日 -
 業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日
業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日 -
 県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日
県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -
 まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日
まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -
 アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日
アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -
 「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日
「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -
 鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日
鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -
 農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日
農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -
 栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日
栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日



































































