JAの活動:米価高騰 今こそ果たす農協の役割を考える
「令和の米騒動」と水田政策の未来 事後調整の必要とJAの機能 西川邦夫茨城大教授に聞く(2)2025年7月17日
政府備蓄米の放出で店頭の米価格が低下し始めるなか、まもなく早期米が出回る時期を迎える。生産現場には今後の米価の動向などに不安が広がるなか、2027年度からの水田農業政策の見直し議論も始まる。改めて今回の「令和の米騒動」の要因と今後の政策のあり方について茨城大学学術研究院応用生物学野の西川邦夫教授に聞いた。
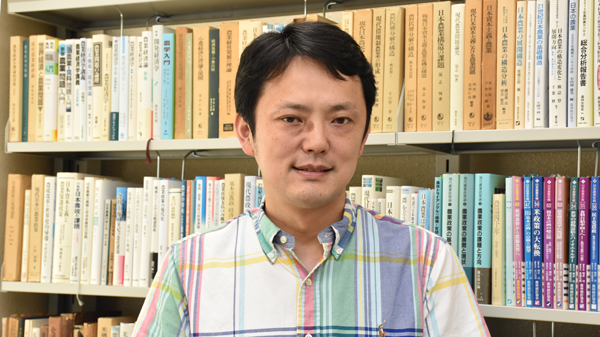 茨城大教授 西川邦夫氏
茨城大教授 西川邦夫氏
――現在のいわゆる「令和の米騒動」のなかで来年6月ごろをめどに水田農業政策の見直しが議論されます。どう見直しを図るべきと考えますか。
交付金 何に着目するか
まず、現行の「基本指針」(米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針)はあくまで目安ではありますが、国がどこまで意図しているかはともかく、拘束力のある生産調整の指標として機能しています。目安や見通しを出すこと自体は問題ないと思いますが、交付金との関係で拘束力を持ってしまう。そこは全体として改めなければならないと思っています。
ですから水田農業政策の見直しのポイントとしては、交付金の見直しと、先ほども触れた用途制限の見直しです。この2つが見直されたら現行の生産調整は廃止されたという評価になっていくと思います。
そして需給調整の安定化については事後的な需給調整の仕組みをどうつくるかです。
2027年度以降の水田政策の見直しについて、農水省の方針は水田と畑を分けないということですね。そうなると必然的に主食用米の作付けは交付金とは切り離されることになるはずです。水田と畑を分けないということは、これまでのように水田のなかで主食用米の作付けはこれだけ、残りは主食用以外を作付ける、それを交付金で支援する、ということがなくなるはずです。
現在の方針は作物別に交付金で支援するということになっていますが、もう少し踏み込むと作物別の交付金もやめて、たとえば農地や所得にターゲットを設定することも考えられます。
そうなると、どの作物を選択するのかは農業者の選択に委ねられることになりますから、より市場に親和的だと思います。
つまり、飼料用米でも麦、大豆でも、何を作るかは地域で話し合って農業者に決めていただければいいということです。その基礎となる部分を政府が農地や所得などに着目して支援する。現在の交付金でいえば水田活用交付金と経営所得安定対策は統合されることになるでしょう。
そこでセーフティネットをどう仕組むかの話になるわけですが、これは結構、難しいと思っています。
消費者米価とのギャップ埋める
直接支払による所得補償は、生産者と消費者の思っている適正価格のギャップを埋めることができるという主張があり、その通りだとは思いますが、一方でそれだけでは生産性が向上しないという主張もあります。
私は直接支払がベターだとは思いますが、現実的にはたぶん「適正価格+直接支払」になると思います。
先日の報道では消費者の米の適正価格は5kg2500円程度で生産者は3000円から3500円だということでした。農水省が公表した2022年産米のコスト調査結果をもとに、物価の上昇や自作地地代などを補正すると2500円ぐらいになります。ですから手持ちのデータで主張できる米価は2500円ぐらいになります。
しかし、それでは農業者にとっては十分ではないという話になるでしょうから、その差を埋めるのが直接支払ということになると思います。つまり、2500円まではコストから考えた適正価格を形成し、それに加えて500円、600円を直接支払いしていく。その場合、直接支払部分をどう説明していくのかがポイントになってきます。
たとえば、2500円では生産原価レベルです。これでは再生産はできますが、長期的な投資などの余力はなく、後継者の確保も難しいということになりかねません。その部分を直接支払で補うという考え方です。
多様な担い手を支援
――対象となる担い手はどう考えますか。
担い手は多様でいいと思います。大規模でなければいけないなど、特定の担い手像を国が決めるということではないと思っています。
石破総理は所得補償をする場合は、生産性の向上とセットでなければならないと言っており、それは理解できます。ただ、それは政策の組み方次第だと思います。
たとえば規模で区切るということはないと思いますが、所得補償の支払い年限を区切るということはあるかも知れません。10年、20年という設定にして、その間に生産性を向上させればコストは下がり、所得補償は必要がなくなるだろうという考え方はあると思います。
その期間に規模を拡大するなり、多収品種を栽培するなどの取り組みを行ってもらうのは一つの案だと思います。
稲作は大雑把に言えば、機械作業と管理作業から構成されています。機械作業だけを考えればまだ規模拡大の余地があると思いますが、問題は管理作業です。水管理に自動システムを導入することはできますが、畦畔の草刈りはできません。そこが規模拡大のネックになると思います。そこで今後はサービス事業体に委託していくことも考えたほうがいいと思います。
重要な農協の安定供給機能
――JAグループに期待されることは?
今回の米騒動と関連させて考えると、やはり農協の安定供給機能に尽きると思います。
農水省の調査では全農に集まった米が30万t足りなかったため、卸が自ら産地で集荷に走り、それで価格が上がった。やはり農協に米が集まらないと流通が混乱するという意味で、農協の安定供給機能は大事だと確認できたと思います。
一方で昨年の出来秋の時点では、とくに東日本で概算金が相対的に控えめだったということは、米市場の混乱を一定程度抑制する効果があったと思っています。概算金の影響力は大きいですから、冷静な判断だったと思います。その意味でも農協の安定供給機能は再度評価すべきです。
水田農業政策の見直しに向けてJAグループはぜひ積極的に提案をしていただきたいと思います。
(にしかわ・くにお)1982年島根県松江市生まれ。2005年東大農学部地域経済・資源科学課程卒。2010年東大大学院農学生命科学研究科農業・資源経済学専攻博士後期課程修了。2014年茨城大農学部准教授、2025年茨城大学術研究院応用生物学野教授。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日
シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日 -
 農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日
農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日 -
 【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日
【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -
 スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日
スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日 -
 5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日
5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日 -
 (472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日
(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -
 山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日
山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -
 大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日
大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -
 栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日
栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -
 大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日
大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -
 愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日
愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日 -
 業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日
業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日 -
 県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日
県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -
 まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日
まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -
 アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日
アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -
 「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日
「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -
 鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日
鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -
 農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日
農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -
 栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日
栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日



































































