【みどりの食料システム戦略―夢満載 そのロマンに賭けるべきか、現実を直視すべきか(1)】対談(下)蔦谷栄一農的社会デザイン研究所代表+谷口信和東大名誉教授2021年5月28日

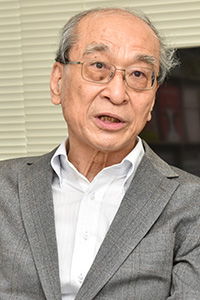 谷口信和 東大名誉教授
谷口信和 東大名誉教授
現場の農業に知見を見出す
谷口 みどり戦略はイノベーションを強調していますが、私はこれまで科学を農業に適用するという思想が強すぎたと思っています。これからの持続可能な農業を考える上では、現場の農業実践を尊重し、その中から科学的な知見を発見するという姿勢が求められているように感じています。こんな古いもの、と思っていた技術が非常にレベルの高い内容をもち、現代の最先端科学できちんと説明できるといったことが大事です。今はどうも逆になっている気がします。
どちらかというと、外から技術を当てはめるという発想で有機農業や環境保全型農業、持続的農業を考えているのではないか。もともと農業は有機農業であり、持続的であったのに、いつのまにか持続的ではないものに変えさせられてきた側面が強い、順番が逆ではないかというのが私の考え方です。
もともと農業が持っていたオリジナルな力を現代科学の光を当てて蘇らせるというような発想が必要ではないかと思います。
 蔦谷栄一 農的デザイン研究所代表
蔦谷栄一 農的デザイン研究所代表
持続可能な農業とは何か それが問題だ
蔦谷 有機農業の定義も問題ですが、それ以上に今回は持続性のある農業とは何かを議論することが大事です。
みどり戦略は生産力向上と持続性の両立をめざすとしていますが、何が持続性なのかということをきっちり整理しないと、過去の歴史が整理できません。先ほども指摘したように環境保全型農業は1992年に登場し、その前から有機農業はあります。法律も有機農業推進法、持続農業法などいろいろです。
ですから、改めてどういう世界を求めるなかで有機農業が出てくるのか、をはっきりさせなくてはなりません。今回は有機農業が突出してしまい、要するに肥料、農薬を使わなければいいんだ、という話になっていないか。そうではなく持続性が肝心要で、地球環境や生態系など、それらを守っていく農業をやりながら、その一つの有力な手法として有機農業があり、それを2050年には耕地面積の25%、100万haにしていこうという組み立てであるべきです。
ところが、今は持続性とは何かという議論がなくて、2050年カーボンニュートラルの目標があり、いきなり有機農業25%ということです。もう少し哲学がいると思います。なぜこういうことをやらなければならないのか。自分たちは日本の農業を持続させるために自然循環を活かす農業をやっていかなければならない、そういうなかに有機農業がある、という話でなければなりません。
いきなり25%という話が出てくるから違和感、唐突感があって、こんなことできるわけがない、となってしまう。
谷口 もはや好き嫌いではなく、私たちは未来に向けて持続可能な農業に向かわなければならない事態に直面しているということですね。
蔦谷 持続可能性とは何かといえば、たとえば自然循環機能の発揮、生態系の維持、生物多様性の保全、温室効果ガスを排出しないといった基本的な課題があって、それをふまえて農薬や化学肥料はできるだけ使わない、できるだけ再生エネルギーを活用するというかたちで農業のあり方にも結びついてきます。輪作やカバークロップをはじめ在来の技術もたくさんあります。
こうしたさまざまな農法の特徴と、持続可能性に関わる要素をマトリックスにして示す作業が絶対に必要だと思います。そして、これらを指数化・指標化して見える化することによって、生産者も消費者も自らの問題にしていく。そうした大きな図柄は国がつくる必要がありますが、具体的な取り組み方策は地方でつくり、それを地域営農計画に落とし込んでいくという流れが求められると思います。
農協に期待される地域を束ねる力
谷口 地域での取り組みが大事だということですが、農協が地域を束ねれば環境保全型農業なり有機農業が一挙に進む可能性はあるのではないでしょうか。
蔦谷 私も農協が本気で取り組めば意外と進むのではないかと思います。そのときに有機農業をあまり強調せずに、むしろ持続性の確保、農薬や化学肥料の適正使用による削減から取り組み、結果として有機農業でも生産できるというかたちにできるのではないか。
谷口 その点で押さえておきたいのは1990年代の米国のLISAの考え方です。これは「Low Input and Sustainable Agriculture」ですが、 低投入と持続的な農業ということですね。
これに対して有機農業の考え方は非農薬、非化学肥料ですからNo Inputということです。しかし、NoではなくてLowでいいのではないか。目標をはっきりさせて年々、下げていけばいい。そうでなければ取り組みは広がらないのではないかと思います。
蔦谷 100人のうち25人が有機農業をするというのはとても難しいですが、100人全員が農薬・肥料を25%削減することはできると思います。そういう意味も含めて持続可能性をキーにした戦略が必要です。有機農業といっても現場での納得感が湧きませんが、持続可能な農業として農薬、肥料を減らす。具体的には防除暦を見直してみようとか、必要最小限に使用をとどめていくという話に落とし込んでいったときに、意外と現場は動くのではないかという感じがします。
有機農業というのは要は本来自然の持っている生命力を活かしていくということが基本だと思います。ですから、今回「戦略」と言っていますが、戦略ではなく目標を出しているだけでこれから戦略をつくらなければなりません。その戦略とは持続可能な農業の定義をはっきりさせ、今まである持続農業法や有機農業推進法などを整理し直すことだと思います。そのうえで地域営農までどうやって落としていくかということですすめれば不可能な目標でもないという気もします。
数値目標に求められる根拠
谷口 ただ、有機農業面積100万ha、農地の25%という2050年目標については、400万haの農地をきちんと担保する方策についてもきちん言ってほしい。みどり戦略にはそういう部分が欠けているので、アドバールーンを打ち上げただけという感じがするわけです。
蔦谷 ゼロエミッションに向けてはCO2の吸収源として農地や草地も重要になってくるわけで、持続可能性の観点からも一定の農地面積を確保しなければならないということを言う必要がありますね。
谷口 持続可能な社会にするために国土全体をどう使うのかということを国民的な議論にする必要があると思います。そのときに農業者、農協の役割、企業の役割は何かを考えていくことが重要です。
そのなかで都市住民に対しても耕作放棄地がどうしてこれだけ大量に発生してしまったかについて無関心ではいられないということを訴えかけることも大切です。
つまり、国産農産物を買うか買わないかという国民的議論が単に食べ物の話に止まるのではなく日本の国土をどうするか、なぜ日本に農業が必要なのかという話につながっていかなければなりません。ややもすると食べ物をどうするかという非常に狭い議論になってしまう。たとえば、消費者は海外のものの方が安いから買うといいますが、他方で高くても海外のものを買っている人もいます。だから、国内農業を消費者はどうして擁護しなければならないかという議論とは、決して食べ物の話だけではないわけです。
有機農業についても、そういうものを食べられる人はいいわね、で終わってしまっている面があります。
蔦谷 その点に関して、みどり戦略では「担い手」という言葉のほかに「支え手」が登場しています。つまり、これから農業の支え手をどれだけ作っていけるかということだと思います。
協同組合間提携も言われますが、買い手としてしか見ていないのではないか。そうではなくて農業も含めて地域の支え手としての協同組合の連携も考えるべきです。
今日は基本計画とみどり戦略は一体ではないかとの見方を申し上げましたが、国民として期待するのは基本計画を議論した農政審議会でこのみどり戦略をもう一度議論するということです。これからますます変化が激しくなるなかで、本質的な問題があれば、その都度、農政審が国民の議論を吸い上げながら審議していくことが大事になっていると思います。
また、農業の世界からも温室効果ガスを4%を排出しているわけですから、そこを農業者も農協も認識して気候変動対策とは自分自身の問題だとの認識をスタートにしてほしいですね。
【対談を終えて】
「現場一流 経営三流」が1990年代以降の日本経済停滞の深層の要因だという▼熟練社員を首切りし、非正規社員を増やし、外注化を進め、末端とトップの距離を広げる効率化に邁進してきた三流社長の姿はコロナ禍に立ち向かう中央政治家・官邸官僚の姿と二重写しだ▼だが、対極に自治体・保健所・病院などの現場で類まれな力量を発揮している方々の雄姿をみると日本も捨てたものではないと思う▼蔦谷さんがみどり戦略の起点を1992年の新政策に見出し、失われた30年という位置づけを与えられたとき、みどり戦略の内実の実現は日本農業再建にとって不可避の歴史的課題だと確信した▼久しぶりに目を見開かせられた対談だった(谷口信和)。
重要な記事
最新の記事
-
 【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日
【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -
 【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日
【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -
 【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日
【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -
 【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日
【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -
 【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日
【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -
 【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日
【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -
 共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日
共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -
 新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日
新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -
 JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日
JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -
 JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日
JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -
 「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日
「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -
 「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日
「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -
 「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日
「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -
 【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日
【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -
 虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日
虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -
 良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日
良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -
 「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日
「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -
 全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日
全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日 -
 第168回勉強会『自律型スマート施設園芸~植物環境工学におけるセンシング・情報の可視化・共有化』開催 植物工場研究会2026年2月16日
第168回勉強会『自律型スマート施設園芸~植物環境工学におけるセンシング・情報の可視化・共有化』開催 植物工場研究会2026年2月16日 -
 佐賀県みやき町の特産品を全国へ「産直アウル」で特集ページ公開2026年2月16日
佐賀県みやき町の特産品を全国へ「産直アウル」で特集ページ公開2026年2月16日






































































