JAの活動:新世紀JA研究会 課題別セミナー
専門農協の事業救ったJA【JAえひめ南代表理事組合長 黒田義人氏】2017年6月7日
総合JAの資金力で
宇和青果と合併のJAえひめ南
◆信用依存に不安も
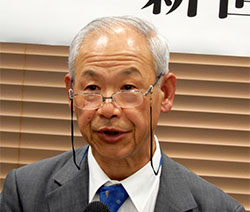 いま起きていることは何なのか。歴史を動かそうとする意思の作用があります。その意思は、大きなうねりへの焦燥であるのかもしれません。それを制御したいとの思いから発したものかもしれません。しかし私は、その目的効果に懐疑的です。希望に満ちた腑に落ちる未来像が見えづらいからです。
いま起きていることは何なのか。歴史を動かそうとする意思の作用があります。その意思は、大きなうねりへの焦燥であるのかもしれません。それを制御したいとの思いから発したものかもしれません。しかし私は、その目的効果に懐疑的です。希望に満ちた腑に落ちる未来像が見えづらいからです。
市町村合併に先んじた平成の農協広域大合併は、金融自由化に備えるためであったと記憶しますが、今日的課題は超低金利政策の継続下で、今後の金融事業や農協経営をどうするかです。総合農協の金融事業依存のビジネスモデルがもう通用しなくなる恐れは十分にあります。代理店手数料と現状の信用事業利益がどの程度違うのか、まだはっきりとは見えていません。しかし、総合農協という仕組みを考えれば、信用事業兼営が望ましい。営農事業を伸張するには、農家の資金繰りに寄与できる仕組みを維持する必要があります。
超低金利政策継続はデフレ脱却、景気回復のためという建前ですが、金融機関が息切れしていく政策には無理があります。資源に乏しく狭い国土に膨大な人口という不利を有利に転換できた成功の戦後史は終わっています。後発工業諸国の追い上げと円高に怯え、財政規律を放擲(ほうてき)し、通貨と国債の増発を止めることができなくなっています。だれがどうやってこの結末の責任を取るのか、取れるのか。円貨暴落時の食糧確保はどうするつもりでしょうか。
世界に広く深くビルトインされた日本経済が世界の地政学リスクを封じ込め、食糧の安定輸入は心配ない、と今でも本気で言い切れるのか。加工貿易立国偏重の中、農業の国家基本政策は弥縫(びほう)策で済まされ、ドゴールからは「魂無き繁栄」と酷評されたものです。この無責任な場当たり的依存主義的生存環境からの脱却こそが「戦後レジーム」からの決別のはずなのに、食糧自給率向上やそれを可能にする国土の隅々まで行き届く強靭な家族農業を支える仕組みへの熱い思いが伝わってきません。それどころか、農政の流れは、総合農協を含む日本農業の維持基盤をないがしろにしかねません。
◆柑橘過剰で危機に
台風が常襲する四国西南暖地の急峻な小山に開花結実する柑橘は、強靭な家族農業の賜物です。それを支える仕組みの到達点が戦後の専門農協でした。この名門柑橘農協の著した「宇和青果農協八十年の歩み」から引用しつつ、その栄光と悲劇を語ろう。そこから汲み取れるものは、信用事業と農協運営の不可分性です。そして組合員の農協利用こそが農協の経営を支え、運営の原資を創出するということです。このことが自明の理として運営されてきたのが広範な総合農協でした。
しかし、この名門農協の歩みはそうではありませんでした。前史ともいうべき時代、すなわち明治43(1919)年、立間村に生産者による「立間柑橘販売組合」が設立され、大正3(1914)年宇和柑橘同業組合が設立されました。その後昭和4(1929)年に宇和蜜柑販売購買組合が設立され、翌年には、「宇和蜜柑販売東京出張員」を東京に派遣しています。
宇和蜜柑同業組合は生産指導、出荷選別規格の普及向上は果したが、産地における生産者対商人の取引形態を改変するものではありませんでした。それは、組合組織の構成が生産者と商人の混合体であったからです。この組合設立後も中央市場との取り引きは商人が一手に握っていました。
販売購買組合の設立を受けて、同業組合の定款改正に向け、生産者と商人の激しい争いになり、その結果、同業組合の蜜柑は販売購買組合を通じて、全量委託販売することになりました。この間、政治の介入があり、新聞には商人に肩入れした論説やそれへの反論記事が出たといいます。独禁法適用強化の今の流れは弱者協同の精神と相容れぬものです。
これを継承した戦後の専門農協は、柑橘の換金性の強さと量を背景に6000人以上の組合員を誇り、市町村域を超えた巨大な存在と作用を有し、農家の生産と家計を支えました。共選場、加工場、首都圏貯蔵所、販促活動など周辺の総合農協の及ぶところではありませんでした。しかし過剰時代の没落が始まりました。平成21年に総合農協の当組合と合併して資金繰りが調(ととの)い、約45億円にまで落ち込んでいた販売高は平成28年度に約68億8000万円となりました。
そもそも、農家の資金繰りが大変だからこそ農協ができたのです。個別農家に代わって在庫を負担し、前渡金を支出し、予約購買を安くし、期限の利益を許与し、月給制を仕組み、当座貸し越しを仕組み、ゆとりある人と金のない人の資金繰りを支えるという相互扶助を実践してきました。
◆資金力が運営の要
組合員の農産物価格安が継続するとき翌年の再生産はどうなるのか、総合農協と専門農協の差が出てきます。農協自体の資金繰りが調うことが運営の永続性を担保するのであり、昭和22年の農協法制定に際し、農林省は単協の信用事業兼営と准組合員制度について必要性を主張しました。時は流れたが、この見解を改める実益はどこにあるのか承りたい思いがあります。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日
シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -
 農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日
農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -
 【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日
【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -
 【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日
【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -
 (474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日
(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -
 和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日
和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -
 築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日
築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -
 幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日
幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -
 「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日
「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -
 大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日
大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -
 築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日
築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -
 栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日
栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -
 秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日
秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -
 農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日
農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -
 日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日
日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -
 中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日
中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -
 持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日
持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -
 札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日
札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -
 高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日
高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日









































































