農薬:時の人話題の組織
【時の人 話題の組織】友井 洋介(日本農薬(株)代表取締役社長) 未来の食と農業を支える2016年3月11日
世界で戦える優良企業めざして
日本にはあまたの農薬会社があるが、社名に「農薬」と謳い、独創的な新剤開発によって、日本はもちろん世界の農薬業界を牽引しているのは日本農薬(株)だといえる。昨年12月、海外での経験が豊富な友井洋介氏が、同社の新しい指導者として社長に就任された。「未来の食と農業を支える力に」を掲げる日本農薬の研究開発や経営のあり方、さらにこれからの農業について忌憚なく語ってもらった。
◆「独自性」の追求と「観察眼」に誇り
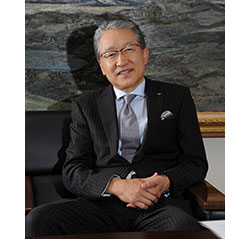 「オリジナリティを追求していることと、研究者の観察眼を高め新たな効き方、作用性を発掘していくこと」が、日本農薬の特徴だと友井社長はいう。
「オリジナリティを追求していることと、研究者の観察眼を高め新たな効き方、作用性を発掘していくこと」が、日本農薬の特徴だと友井社長はいう。
インタビューのなかでも「オリジナリティ」や「独自性」という言葉がしばしば語られていたことが印象深かった。
日本農薬という会社は、1920年代初頭に古河鉱業(現・古河機械金属(株))の銅の精錬による副産物を活用して日本で最初の登録農薬「砒酸鉛」の工業化に成功したことを機に、砒酸鉛を事業化していた旭電化工業(現・(株)ADEKA)の農業薬品部門と藤井製薬が合併し、1928年(昭和3年)に日本最初の農薬専門企業として誕生する。
この当時は農薬という言葉はなく「農業薬品」といわれていたが、「農薬」という今日まで使われている言葉を会社名として初めて使ったのも日本農薬であり、現在、国内で農薬を開発・製造している企業は多いが、社名に「農薬」と明記しているのは、日本農薬だけだ。
理化学研究所などと協力して、水稲用殺菌剤であるブラストサイジンSといった抗生物質を農薬として開発したのも同社だ。
さらに1960年頃までは欧米企業が開発した農薬のライセンスを得て事業展開してきたが、「自前で開発をしよう」と、研究開発に積極的に取組み、1974年(昭和49年)、創立50周年を祝うように誕生したのがいもち病防除剤の「フジワン」だ。このフジワンは「他に類似の化合物はない」というオリジナリティに富んだ新たな化合物だった(フジワンの研究開発については本紙2013年11月20日号「誕生物語」を参照)。
そして友井社長が強調する「高い研究者の観察眼」の威力が発揮されるのが、フジワンをほ場で使用するなかで「田んぼでのウンカの増え方が少なくなり、ウンカの密度を抑制する効果がある」ことを見つける。そして「効果発現まで長い目で見る必要がある」ということで、スクリーニング方法を工夫することで、殺虫剤のアプロードが発見される。
いま日本農薬の主力製品となっている殺虫剤フェニックスも、「除草剤としてスクリーニングしているうちに虫に活性がありそうだ」ということから展開されたのだという。
もちろんすべてではないが、フェニックスや、昨年上市されたダニコングなど、「当社は独自の化学構造を追求してきている。それが社風になっているし、誇りにしている」と友井社長は胸を張った。そして「世界で勝ち残っていくためには、こうしたオリジナリティを大事にしていきたい」とも。
◆「捨てる」開発と丁寧に「拾う」開発
研究開発については、欧米のグローバル企業と日本企業では、基本的な発想が違うと友井社長はみている。
欧米の企業はどちらかというとメッシュが粗く、「捨てるスクリーニング」をしているので、大きなものが残る。そこには欧米の企業は事業規模が大きいため、ある程度の販売額になるものでなければ事業化できないという事情があるからだ。
それに対して日本での研究開発は、事業規模が小さいことや「日本人の丁寧な特質」もあって、「拾うスクリーニング」をし、欧米企業なら見落とすようなものでも違う視点から「拾って」くることで、結果として多くの剤が開発されてくるのではないかと友井社長はみている。
そして「世界の企業と同じことをしていてもしょうがない」のだから、独自の道を歩んでいると自負している。確かに日本農薬が国内・海外で販売している農薬の70%以上は自社開発製品となっている。
農薬が製品化されるには、研究段階から10年以上の歳月がかかる。研究初期段階で10年先をどう読むのだろうか? 友井社長はこう説明する。
最近は「プロダクトアウトからマーケットインへ」とよくいわれるが、農薬の場合、農薬登録され製品化できたものを適用拡大するとか、混合剤を作るときには、当然、マーケットインの考え方でやっていくことになる。しかし、10年先、15年先をマーケットインの発想だけで予測することは難しい。むしろ「こういう剤があったら絶対に将来役に立つと考えて開発をする」というプロダクトアウト的な発想をすることが正しい...と。
昨年9月末の日本農薬グループの連結売上構成をみると、国内農薬販売34.9%に対して海外農薬販売43.3%、化学品・医薬品他18.7%、その他3.1%と、農薬については海外のウエイトが高くなっている。日本農薬グループのグループビジョンでは「世界で戦える優良企業へ」、そしてグループの中期3カ年計画でも「グローバル企業への前進」を掲げている。
「日本農薬は日本をベースにしている会社ですから、国内市場を大切にしていますし、国内で事業がきちんとできないと海外に行っても本当の意味でグローバル企業にはなれません」と、友井社長は国内農業への貢献が経営基盤の根っこだと強調する。
そのうえで、日本国内は人口減少などから「そんなに大きく伸びる市場ではない」。一方、世界的には新興国を中心に人口増加が予想されており、これを支える食料増産は大きな課題となっている。「世界の食料生産に貢献できる会社になりたい」ということだ。
新剤を1剤開発するには、「欧米のビッグカンパニーでは200億から300億円開発費をかけている」といわれている。そこに伍して、世界で売れる剤を開発するには少なくとも100億から200億円は要るという。日本農薬では「経営の苦しいときでも売上高の10%を研究開発費にかけてきた」。今後もそうしていくためには「伸びる海外をターゲットにして伸びていき、そこで売上げはもちろん収益をあげて、次の新剤創出の原資を蓄えていく」。それが海外市場への展開をめざす基本的な考えだという。
さらに新興国は、品質もあるが「どちらかといえばコストの低いものがよく売れる市場」でもある。もちろん「オリジナリティのある高付加価値製品を提供していくのは当然だが。同時に品質の高いジェネリックも供給することで、販売のボリュームゾーンを伸ばしていく」ことも考えている。そのためにインドの農薬製造会社の買収やブラジルの製造販売会社へ共同出資をしている。
つまり、国内をコア市場としながら、海外で収益をあげ、日本農薬らしい独自の新剤を創出していく。そして「将来的には世界のトップ10に入り、世界で戦える会社にしていく」のが友井社長の構想だ。その友井社長がいま注目しているのが、ブラジルとインドだ。ブラジルは「経済が減速している」といわれるが、いままで急速に成長してきたので、いまは「調整期」だと友井社長はみている。
◆効果的効率的な省力化技術実現へ
あまり伸びてはいかないだろう、と予測する日本農業の将来についてどう考えているのか聞いてみた。
生産者の高齢化が進み、担い手が少なくなっていくなかで、日本農業が生き残るには、「規模拡大だけが道だとは思わないが、一定の規模拡大をしていかざるをえない」とみている。もちろん規模拡大といっても「米国やブラジルのような国と比べても意味がない」と認めてのうえだ。
「一定の規模拡大」をすると「省力化技術が必要になってくる」。例えば水稲では、今後は直播型栽培が増えてくるとみている。そうなると現在の水稲用除草剤は移植栽培用になっているので、直播に適用できる新剤の開発をしていかなければならないし、高齢化が進めば1回の防除ですむ省力型農薬がますます志向されると予測する。 さらに移植でも直播でもロボット化(自動化)に対応する技術や、ドローンを活用した農薬散布やさまざまな栽培技術が開発されてくるとも予測している。
最後に、全国の生産者そしてJAグループへのメッセージを聞いた。
日本農薬は「1964年に、商系メーカーとして初めて農協(系統)と取引きを始めました。それ以来、長い間JAのみなさんとお付き合いをさせていただいてきています。いま農業が変わらなければいけないといわれていますが、そのためには農業用資材をより効率的に効果的に使えるように指導していく必要があります。生産者といってもすべての人がプロではないので、JAの果たす役割は大きいと思います。品質の高い農作物を生産し、日本農業の競争力を高めるために、ぜひ私どもにも協力させていただきたいと考えております」と、語ってくれた。
(ともい・ようすけ)1956年生まれ。1980年香川大学大学院農学研究科修了、同年日本農薬(株)入社。1995年海外事業部ニューヨーク事務所長。2002年企画管理本部経営企画部長。2006年執行役員 社長室経営企画部長。2007年取締役兼執行役員 社長室長。2009年取締役兼執行役員 営業本部副本部長。2011年取締役兼常務執行役員。2014年取締役兼専務執行役員。2015年代表取締役社長。
重要な記事
最新の記事
-
 百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日
百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -
 将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日
将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日 -
 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日 -
 【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日
【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日 -
 【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日
【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日 -
 アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日
アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -
 振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日
振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -
 愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日
愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -
 葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日
葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -
 「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日
「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -
 初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日
初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日 -
 【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日
【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日 -
 農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日
農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -
 食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日
食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -
 まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日
まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -
 クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日
クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -
 「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日
「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -
 邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日
邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -
 藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日
藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -
 東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日
東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日





































































