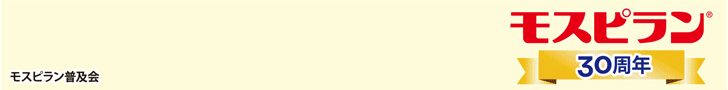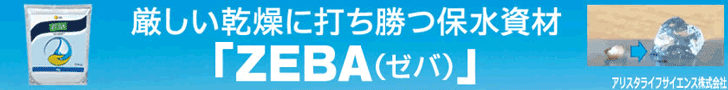【新規就農者対策】「あらゆる政策資源で人材確保」佐藤一絵・農水省就農・女性課課長2018年6月22日
・佐藤一絵農林水産省経営局就農・女性課課長
おおむね5年ごとに見直すことになっている食料・農業・農村基本計画の議論が来年(31年)春から始まる見込みだ。基本計画は食料自給率目標のほか、農地や担い手、農村振興策や新技術などについても目標を掲げ、農業・農村の持続的発展と食料の安定供給の実現をめざす。ここでは焦点の問題について現状と今後の課題を、随時、政策担当者など関係者に聞いていく。今回は新規就農者確保について農水省の佐藤課長に聞いた。
--平成22年には260万人いた農業就業人口は29年には181.6万人に減少しました。
「平成25年に政府が決めた『農林水産業・地域の活力創造プラン』において、平成35(2023)年までに49歳以下の青年就農者を40万人に拡大しようと目標を掲げましたが、現時点では正直、目標達成に向けた道のりは厳しいと言わざるを得ません。もちろん、ここ数年、さまざまな政策資源を傾けた成果もあり、特に非農家出身で新規に雇用就農の形で農業を職業として選択してくれる若者が増えるなど、減少傾向から反転はしていますが、それでも現時点では約32万人であり、目標達成までには相当高いハードルを超えなくてはなりません」
(写真)佐藤一絵 農林水産省経営局就農・女性課課長
-日本全体が急激な人口減少に進む中で、産業界全体が人手不足に悩まされているわけですが、農政として打ち出した担い手確保策について実績をどう評価しますか。
「状況を重く受け止め、直視しなくてはならないと考え、より大胆な政策を打ち出すことになりました。その一つが平成24年度からの『青年就農給付金』(現・農業次世代人材投資資金)事業です。これは農業を始めるための準備期間の最長2年間(準備型)、実際に経営を開始してからの最長5年間(経営開始型)、それぞれ最大で年間150万円を個人に支給するもので、他産業にはない強力な支援措置と言えると思います。現在、全国に受給者は準備型、経営開始型双方で約1万5000名いますが、制度開始から7年目となり、この事業で支援を受けて来た新規就農者がいよいよ本格的に自立経営を始める段階になってきています」
-一方、28年に政府として決めた「農業競争力強化プログラム」のなかで、農業人材については、教育システムの充実、就職先として農業法人の強化、女性の活躍推進も含めた次世代人材投資、農業者の視野の拡大など、7つのポイントが示されています。この競争力強化プログラムでの基本的考えとはどのようなものでしょうか。
「これからは、担い手が少ないなかでも、生産量や品質を落とさず、効率的な農業を推進していくことも必要です。農業者の量的な確保への努力はもちろん、農業者一人ひとりの『質』やスキルの向上も必要です。農業者の減少により、スマート農業の進展や1経営体当たりの経営面積が拡大していかざるを得ないであろう状況を踏まえると、今後の『農業人』の姿は、生産技術が優れているだけではなく、先端的なITや機械などに対する知識、さらに経営感覚にも長けたマルチな才能をもった人でないと務まらないのではないか。ただ、そうした状況になれば、農業人としての成功がステータスとなり『職業として農業を選択する』という流れが若い世代にできてくるのではないかと期待していますし、そういう流れを作りだしていかねばと思います」
--来年度から始まる「専門職大学」制度とはどのような制度ですか。
「専門学校などが、一般の大学と同様に、『学士』の称号を出せるようになります。道府県立の農業大学校は全国に42校ありますが、その中から専門職大学に転換し、実践的な教育で未来のモデルとなるような農業経営者を輩出する方向につながればと思います。静岡県が先行して転換を検討しており、当省としてもサポートしていきたいと考えています」
「私は農林水産省に入省して丸10年になりますが、農業界に対して思うことの一つは『褒め合う文化』が少ないのではないかという点です。出る杭を打ってしまうのではなく、逆に農業界にスーパースターが出てきたら、それを大いに歓迎する新しい土壌が必要ではないか。そういうヒーロー・ヒロインの登場が農業の魅力の『見える化』につながり、後につづく人材供給の突破口を開くのではないかと思うのです」
-政府の働き方改革のなかで「農業の『働き方改革』検討会」も昨年12月に設置され、この3月に意見が取りまとめられています。今後の展望とJAに期待することなどもお聞かせください。
「すでに専業的な農業者のうち65歳以上の方々が66%を占めて、49歳以下は11%しかいません。さらなる農業者の激減に直面するのは必至で『もはや待ったなしである』という強い危機感は当然、農業関係者と共有していますし、あらゆることをやっていかねばならない。その中で、新規就農者の方々にとって、やはりJAの後ろ盾があることの安心感はとても大きいという声を聞いており、若い世代が農業を職業として選択してくれるよう、JAさんとも連携して取り組んでいきたいです。農業の『働き方改革』を分かりやすく解説したワークブックもまもなく出ます。こうしたものをJAの研修などに使ってもらえれば嬉しいですね」 「正直、農業人材確保に向けた即効薬としての処方箋はありません。ありとあらゆる政策資源を切れ目なく投入して、続けていくこと。それに尽きると思います」
【さとう・かずえ】
昭和44年生まれ。
札幌北高校、北海道大学法学部卒。大学卒業後は北海道新聞記者として活躍。その後、出版社勤務を経て、平成20年農水省入省。休日はウォーキングを楽しむ。座右の銘は「意志あるところに道あり」。
(関連記事)
・【人事異動】農林水産省(18.06.22)
・【人事異動】農林水産省(6月15日付)(18.06.15)
・カビ毒と食中毒菌のリスク管理技術で再公募(18.06.12)
・主食用米作付け 前年並み34県-第2回中間的取組状況(18.06.05)
・担い手への農地集積 伸び鈍化-農地中間管理機構 29年度実績(18.06.01)
・【平成30年度農薬危害防止運動】農作物・生産者・環境の安全を(18.05.31)
重要な記事
最新の記事
-
 米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日
米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -
 (471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日
(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -
 スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日
スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -
 【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日
【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -
 【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日
【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -
 【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日
【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -
 【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日
【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -
 令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日
令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -
 「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日
「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -
 2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日
2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -
 【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -
 福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日
福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -
 いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日
いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -
 三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日
三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -
 【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -
 【人事異動】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -
 和牛農家と海外バイヤーをつなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始2026年1月30日
和牛農家と海外バイヤーをつなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始2026年1月30日 -
 酪農業の地域特有の課題解決へ 酪農家との情報交換会「第5回MDA MEETING」地域別開催 明治2026年1月30日
酪農業の地域特有の課題解決へ 酪農家との情報交換会「第5回MDA MEETING」地域別開催 明治2026年1月30日